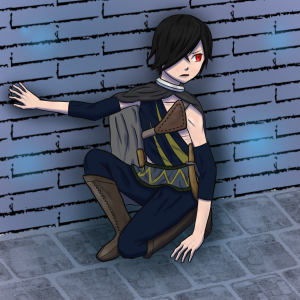
荒野をひたすら南に進むと、エウフラーテス川に突き当たった。
そこから川に沿って、さらに行軍は続いた。
ローマ軍として渡河した時とはまた違った景色だが、この川の周りには豊かな大地が広がっている。起伏のある草原に、ポプラ、ギョリュウなどの低木が点々と生え、獅子や兎、蟻んこといった、大小さまざまな動物がそこに息づいている。
川沿いに進んで五日ほどが経った頃、パルテミラ軍はこの広い草原で狩猟祭を催した。
狩猟好きな女帝の気まぐれで急遽決まった催し物だが、それが本来は軍事訓練を兼ねたものであることを、オレはすぐに知ることとなった。
低木林の向こう側から、だんだんと近付いてくる笛の音。
その音に追い立てられるようにして、鹿の群れが飛び出す。
だがその先には、人を乗せた鹿の大群が待ち構えていた。驚きと困惑で立ち往生する哀れな鹿たちを、変な鹿の大群が瞬く間に包み込んだ。そして変な鹿に乗った人間が、次々に馬を走らせて矢を射かける。
包囲の中でなす術もなく狩られていく鹿たちは、まさに先日の戦のローマ軍だった。
「いつまで鹿と呼んでいる。我々が乗っているのは霊羊だ」
そう教えてくれたのは、先日の戦いでパルテミラ全軍を指揮したスレイナだ。
霊羊とは、テシオンの東にある、アシュタウィア山脈に棲む動物らしい。言われてみれば、確かに角は枝分かれしていないし…………すまないが、それくらいしか鹿との違いが見出せなかった。
先日は総勢一万一千の兵がローマ軍と戦ったというが、そのうちの九千までが、この霊羊に乗った軽騎兵だった。狩りを見ていても、一人としてスパルタクスの将軍たるオレに劣る騎手はいない。よくもこれだけの練度の騎兵を、これだけ揃えたものだ。
宴のあとで聞いた話では、彼女たちも女精といって、幼精と同様、魔法を介して生まれてきたらしい。見かけ上は、やたら美女が多いこと以外、特に変わったところはないのだが……
霊羊に乗るには重そうな女帝は、やはり馬に乗っていたが、馬術も弓術もなかなかのものだった。部下たちに混じって狩りを楽しんでいる。
やがて鹿を三頭ほど仕留めてから、暇そうにしてるオレに、弓と矢筒を投げてよこした。
「お前もやってみたらどうじゃ? どれほどの腕前か、私に見せておくれ」
オレは危うく矢筒を取り落とすところだった。
おいおい……オレはまだパルテミラに降ったわけじゃないんだぜ? そんな奴に武器を与えていいのかい? 射っちゃうぞ?
もっとも、オレにはそんなことをする度胸も動機もなかった。
「御意!」とカッコよく応じて、包囲の中に馬を飛ばした。
さてと……どいつにしようか。
獲物を探すフリをして、狩猟祭が終わるのを待っていると、鹿の群れの中に一頭の猪を見つけた。こちらに向かって突進してきている。
あれなら狙いやすそうだ。
仕方なく、オレは弓に矢をつがえ、馬を走らせた。
弓術にはそれなりに自信があったが、疾走する馬の上から射るのは初めてのことだった。
左手に弓、右手に矢を持ち、脚だけで馬を操る。ここまではなんとかできた。
あとは簡単だ。まっすぐ突っ込んでくる的に、いつも通り――
ガクンッ
矢を手放したのと、着地の衝撃で手元がブレたのと、ほぼ同時だった。
狙いすました矢は、猪の手前の地面に落ちていった。
今だとばかりに飛び掛かる猪。その鼻が、オレの腹に深々と突き刺さった。
* * *
その日、オレは捕虜になってから始めて、部下との面会を許された。
あんな無様なやられ方をしたってのに、スパルタクスの仲間たちは変わらずオレを慕ってくれていた。心の中では、馬鹿だの間抜けだのと言っているのかもしれないが……とにかく、元気そうでなによりだ。
スパルタクスの捕虜は、このままエウフラーテス川沿いの都市に移送される。移動は厳しく制限されるようだが、ある程度の自由は約束されていた。
ただ、オレの場合は、女帝の誘いを受けるか否かで、待遇が変わる。
スパルタ戦士としての意地を貫くならば、部下たちと行き先は同じだが、もし、パルテミラに忠誠を誓うのならば、ここで部下と別れ、女帝の本隊について行くことになる。
行き先は、男人禁制の帝都――テシオン。
特例中の特例で、五百人の部下たちも一緒にというわけには、当然いかなかった。
スパルタ戦士の鏡であるオレは、丁重に断ろうと思ったのだが――
「行ってください! ベテルギウス将軍!」部下たちが、背中を押してくれた。「あなたが行かなければ、誰が行くんですか!? こんな機会は二度とないはずです。どうかオレたちの分まで、テシオンを満喫して来てください!」
そうだよな!
ジェロブも、まず間違いなくテシオンに行くのだから、ついて行かないという手はない。
こんなありがたい誘いを断るのは、愚の骨頂というものだ!
オレの心は決まった。
愛と勇気で結ばれたベテルギウス軍団は、これでしばしの解散となる。
「お前たちぃ~! 愛してるぞぉ~!」
別れ際、オレは女たちが見ているのも構わず、五百人の同胞すべてと熱い抱擁を交わした。
そうだ。今度会う時が来たら、テシオンでの暮らしがどんなだったかを話そう。
もし帰ることができたのなら、故郷のみんなにも話そう。
この日から、オレは日々の体験を記録するようになった。
カルデアの荒野での戦いまで遡って、美しいパルテミラの地で起きた出来事を、汚れた心の声を添えて、羊皮紙に洗いざらいぶちまけた。
そう、今書いているこれだ。
これが後世、貴重な史料として衆目に晒されることになるとは、オレは知る由もなかった。
* * *
帝都テシオンは、エウフラーテス川の北を流れるもう一つの大河――ティグラス川の畔にあった。
到着したのは日が沈みきったあとのことだ。
城門へと続く道はポプラの並木に挟まれ、奥では満開のラーレ(チューリップ)の花が咲き乱れている。太陽の下で見たならば、さぞかし楽園にでも迷い込んだ気分になっただろう。
だが闇の中で淡く光る姿も十分に美しく、長旅で疲れたオレの心に安らぎを与える。
月の光を吸い込んで、氷のように光るテシオンの城壁は、邪な心を持つ者の侵入を阻んでいるかのようで――そう、オレみたいな人が入ってはいけない、まさに聖域のような雰囲気を纏っていた。
穹窿が組まれた城門を抜けると、道の左右に並んだ兵が、勝利を持ち帰った戦士たちと、そこに紛れたオレを静かに出迎えた。
夜遅いということもあってか、諸々の最終確認が済むと、すぐに解散となった。
帰る場所のないオレは、案内役を付けてもらって、宿場街へと向かった。一応、軍用の宿舎もあるのだが、女たちと相部屋になったりと、いろいろ不都合があるようだった。
テシオンの街は、夜であっても、それなりの人出で賑わっていた。
肉をくるんだパンを食べ歩く人々。禍々しい水晶玉を抱えた老婆が居座る怪しい店。酒場から流れ出る下手くそな歌声。青白い光に照らされた石畳の道で、それぞれが夜を楽しんでいる。
ただ異様だったのが、大人の男の姿をした者が、オレの他には見当たらないことだ。すれ違うのは、女精か幼精か女か。あえて言うならば、年老いた幼精が一人いたくらいだ。テシオンまでの道中では、男も普通に見かけたのだが。
なぜ、オレだけが入ることを許されたのだろう。
パルテミラの男を差し置いて、なぜ侵略者だったオレが……?
道行く人がオレを見る目は、どれも友好的なものではなかった。女の付き人がいなければ、卵でも投げつけられていたんじゃなかろうか。
そう思っていたら、露店のおばさんが、笑顔で林檎を投げつけてきた。
「持って行きな。色男」
なんだ……そういうことか。
ありがとう、綺麗なおばさん!
宿場街まで来ると、流石に静かだった。よい子はお休みの時間だ。
こうも静かだと、気にも留めていなかったものが目に付く。
夜道を照らすこの青白い光は、一体なんだろう?
夜間の行軍や宴でも見た、宙を漂う不思議な光。
「あれは『導きの光』。我々女精と幼精が使う古代語魔法の一つです」
案内役の女が、そう教えてくれた。
彼女の名前はエクサトラ。服装からして軽騎兵だ。淡い褐色の髪をおさげにしていて、かなり若く見える。慣れない役回りでやや緊張しているようだが、それが妙に可愛らしい。
「ほう、君たちは魔法が使えるのか! この前の戦では、特にそれらしいものを見かけなかったが……」
「魔法と言っても、そんな大したものではありませんよ。動物と心を通わせたり、体を軽くしたり……精霊の力を少しだけ借りた、目に見えない程度のものです。でも、その道を極めた人たちは、本当にすごいです」
いや、あんたも十分すごいよ。
あんなにピョンピョン跳ねる動物を乗りこなすんだからな。しかし、それができる理由が、なんとなく分かった気がした。
エクサトラは、宿の手配に結構手間取っているようだった。
事情を説明しても、他の客が驚くからと渋られ、直接客と交渉しようにも、よい子は寝る時間というありさまだ。彼女も早く寝たいだろうに、なんだか申し訳ない。
やはり、百年にもわたって男人禁制を守り続けてきた都は、いきなりやって来た男を、すんなりとは受け入れてくれないようだ。
まあ、贅沢は言わんさ。入れてもらっているだけでもありがたいことだ。
交渉が終わるまで、オレは外でしばらく待つことになった。
おばさんからもらった林檎をかじりながら、明日はどうしようかと、思いを巡らせる。
さっきの市場にもう一度行ってみようか。夜とはまた違う光景が見られるかもしれない。王宮に押し掛けてみるのも一興。そのあとは、ジェロブ探しの旅にでも出よう。
林檎をかじる音に混じって、砂利を踏む音がしたのは、その時だった。
壁に沿って、こちらに歩いてくる小さな影がある。
幼精だ……可愛い!
そう思うのも束の間、オレはすぐに彼の纏う、異様な空気に気付いた。
夜闇に溶け込む黒ずくめの服は、少年の華奢な体を引き立たせていたが、身を飾るよりは、動きやすさを想定したもののように思えた。外套の裾に隠れて、短剣も見える。黒髪の下に煌く赤い瞳は、豹にも似た鋭い光をたたえている。
「そこを動くな。パルミュラの亡霊め」
オレに言ってんのか?
考える時間は、与えられなかった。
少年が短剣を抜き、猫のような敏捷さで突っ込んできたのだ。
オレは体を開いて、最初の刺突をかわした。さらに跳び退って、続く第二撃もかわす。
「おい待てって! パルミュラがなんだって? オレはスパルタクス人だぞ」
「どちらにしろ敵じゃないか! くたばれ、ローマの犬め!」
いや、そうなんだけど、そうじゃないというか……今はパルテミラの犬なんだよ。
なんて言っても、分からないか。話を聞いてもらえる状況でもない。
まだ粗っぽさはあるが、少年の剣技は、オレの命を脅かすに十分な域に達していた。
二本の短剣で、攻めて攻めて攻めまくる。左右で癖の違う剣筋は、見切ることを許さず、オレはほとんど反射だけでかわさなければならなかった。息つく暇もない。
このままでは遅かれ早かれ死ぬ。背を向けて逃げても死ぬ。ならば――
オレは大きく跳び退って、追ってきた少年に林檎を投げつけた。
少年は不意を突かれたようだが、短剣を鋭く一閃して林檎を両断した。
いい反応だ。だが見えた!
少年の勢いが弱まった、その一瞬。オレは少年の懐に飛び込み、両の腕を封じ込んだ。
そのまま突進をかまし、地面に組み伏せる。
剣だけじゃない。オレは総合格闘術でも、同期の中では一番だったんだ。ちょうどこの前の狩猟祭でも、猪を素手で仕留めたばかりだ。飛び道具なんて卑怯なものに頼らず、正々堂々と戦ってな。
「落ち着けって。オレが一体なにをしたって言うんだい? 武器も持たない善良な市民を襲うなんて、酷いじゃないか」
「黙れ! 男の身でありながらテシオンにいること。それだけでも、お前に剣を向けるに十分な理由だ!」
腕の中で少年がもがいた。意外と力は強かったが、オレの固め技の前ではまったくの無力だった。幼精と言えど、力は人並みらしい。
「放せ畜生!」
「殺されると分かってて放す馬鹿がいるか。まずはお前が武器を手放せ。それからだ」
そう言うと、少年の体から力が抜けた。
やっと観念したか――そう思って、技を解いた時。腹の底から、重い衝撃が伝ってきた。
「……っ!」
少年が、オレの股間を膝で蹴りつけたのだ。
恐ろしく正確な金的だった。体罰で鍛えられたオレじゃなければ、一瞬で気を失っていただろう。流石にこれは痛…………くない! 気持ちいい!
くそ……スパルタ戦士をなめるなよ。こんなもの……こんなもの……
いつの間にか、少年はオレの腕から抜けて、止めを刺す構えを見せている。
オレはあまりの気持ちよさで悶えて、動けない。
絶体絶命。まさにその時――
「エミール! なんてことをしているの!? その方は客人なのよ!」
それは宿の交渉から戻って来た、エクサトラの声だった。
「客人……?」少年は怪訝そうな顔を、声のした方へ向けた。「そんなわけないでしょう? たとえ外国の賓客であっても、テシオンに男が入るのは禁じられているはずです」
「ええ、でも女帝陛下がお許しになったのよ」
「陛下が!?」
「ほら早く剣をしまって! その方に謝りなさい!」
少年は短剣をしまったが、ブスッとした顔のまま謝る気配がない。
エクサトラは深いため息をつき、先に頭を下げた。
「すみませんでした。私がそばを離れてしまったのが、そもそもの過ちです。男の人がこの街を一人で出歩くには、問題が多過ぎますのに」
「なに、男の身でこの都に入るからには、これくらいの洗礼はあって当然だろう」
悪くない冗談を言ったつもりだったが、二人の反応は薄い。
オレは寝転がったまま、一つ咳払いをして、話を変えた。
「そこの少年が、パルミュラがどうのと言っていたが、なんのことだ?」
「パルミュラは、パルテミラの建国とともに滅びた旧い王国です。近年、その残党による破壊活動が活発になっていて、テシオンでも力のある者が少なからず殺されているのです」
エクサトラは黒髪の少年の頭をペチッと叩き――
「この者は、テシオンに忍び込んだ旧パルミュラ勢力を排除する任務に当たっていました。あなたを襲ってしまったのも、パルミュラの男だと勘違いしてしまったからなのでしょう」
道理で……街の人たちがオレを警戒するわけだ。
ただでさえ男を見慣れていないのに、それが異国のカッコいい軍服を着た色男となれば、平気な顔をしてはいられないだろう。おいしい林檎を投げつけられるのも無理はない。
オレはなんとか体を起こし、相変わらずそっぽを向いたままの少年に、手を差し伸べた。
「あんた、エミールっていうんだよな? さっきはすまなかったな。幼精と人との違いはあっても、一応は男同士なんだ。仲良くやろうぜ」
ペチンッ!
手と手が弾ける、いい音がした。
「……男なんてのは、薄汚い欲にまみれた愚かな生き物だ。一緒にするな!」
少年の赤い瞳に宿っていたのは、憎悪や嫌悪といった、負の感情が凝縮されたような光。
「ちょっとエミール! いい加減にしなさいよ!」
エクサトラが叱りつけるが、すでに少年は背を向け、夜闇の中に走り去るところだった。
あとには陰鬱な空気が、亡霊のように、いつまでも消えずにわだかまっていた。
「すみません、何度も」と、かわいそうなエクサトラ。「あんなエミールは、私も初めて見ました。いつもは真面目で分別のある、いい子なのですが……」
「オレは大丈夫だ。スパルタクスのハゲ教官から浴びせられた罵詈雑言に比べれば、可愛いもんさ」
なんて言ってみたが、全然そんなことなかった。
被虐趣味という輝かしい称号を持つオレでも、あんな真っ向から存在を否定されては、流石に傷付く。肉体的な痛みはいくらでも我慢できるが……
エクサトラが懸命に探してくれたおかげで、この日は無事に宿が見つかった。
他の宿に比べれば質素な所だったが、質実剛健な生活が染み付いたオレには、これくらいがちょうどいい。市場からそれほど離れておらず、路地を抜ければ娯楽施設が並ぶ通りに出る。なにをするにも、不自由はなさそうだ。もっとも、当分は一人で出歩けないのだが。
部屋に辿り着くや否や、オレは邪魔な鎧を床にかなぐり捨てて、寝台に華麗な飛び込みを決めた。
はっ、しまった……体を洗うのが先だ。
そう思い直すが、極上の寝心地を覚えてしまった体は、起き上がることを完全に拒否している。こればっかりは、抗えない。
―――男なんてのは、薄汚い欲にまみれた愚かな生き物だ……
脳裏にこびりつく、エミールの言葉。
何度も現れては、オレの胸を抉っていく。そろそろ風穴が開きそうだ。
―――男なんて……男なんて……男なんて……
ああ、その通りさ!
所詮はオレも、欲望に忠実に生きることしかできない、弱っちい生き物だ。
けどよ……それがなんだってんだ!?
男の欲望が薄汚いだなんて、一体誰が決めたんだ!?
男に生まれるか女に生まれるか、はたまた蟻んこに生まれるかも自分では決められないのに、なんでそんな言われ方をしなければならないんだ……!? 蟻んこだって、必死に生きてるんだぞ!
昂りかけたオレの心を鎮めたのは、夜のしじまに優しく響く、竪琴の音だった。
耳を澄ませば、少年らしい甘い歌声もかすかに聞こえる。
隣の部屋からだ。そこに泊まっている幼精は、そこそこ名の知れた吟遊詩人らしい。廊下で少しだけ話をしたが、各地を渡り歩いた経験からか、まったく男見知りしなかった。
……いい声だ。
エミールの言う通りだ。やっぱり、彼らはとても同じ男とは思えない。オレが大人になって失ったものを幼精は持っていて、オレが少年期に持ち得なかったものですら、彼ら幼精は持っている。
オレは心底、君たちが羨ましい。
だからこそ惹かれるのかもしれない。かつての自分に重ね合わせて――
こんなオレにも、美少年ともてはやされた時期があった。
訓練生時代、将来有望な戦士として知られるよりも先に、むさ苦しい訓練所に咲く花として、オレの名はその界隈に知れ渡っていた。年長の訓練生から告白を受けたことは一度や二度ではなく、そのうちの何人かは、今やオレの忠実な部下になっている。
それから、今ではすっかり見る影もないが、オレは清廉な心を持った少年でもあった。
男は欲にまみれた愚かな生き物――オレも当時は、そんな風に思っていたのかもしれない。一番身近な男がまさにそうだったし、歴史を顧みても、酒色に溺れて破滅した男は枚挙にいとまがない。子供心に、男が醜く愚かなもののように思えたのだ。
だからオレは、穢れを知らぬ純粋な少年であり続けたいと願い、周りもそれを期待した。
しかし時の流れとは残酷なもので、オレはほんの数年のうちに、少年の輝きを失った。
声、容姿、体つき……称賛の的となっていたあらゆるものが、男のものへと変貌していく。自分が自分でなくなっていく。それはもう、抗いようのない運命だった。
あの苦しみは、大人になれない幼精には一生分からないだろう。
おお、神よ! どうせ奪い去るのなら、どうして私に美を授けたもうたのか!
おお、神よ! あなたはなんて酷い奴なんだ!
それからしばらくは、荒んだ日々が続いた。
厳しすぎた訓練をサボっては、遊び呆け、多くの人を失望させた。
でもそんな中でも、あの人だけはオレを見放さなかったんだ。
家に押し掛け、オレを訓練所に引っ張り込むこと数十回。オレはそのありがたみも知らずに、胸筋大魔王なんてあだ名をつけて、馬鹿にしていたっけな――ソグナトゥス先生。
結局、なんで立ち直れたんだっけ。
とにかく、ソグナトゥス先生の熱意に突き動かされ、訓練に打ち込むうちに、悩みなんて吹き飛んでしまった。

コメントを残す